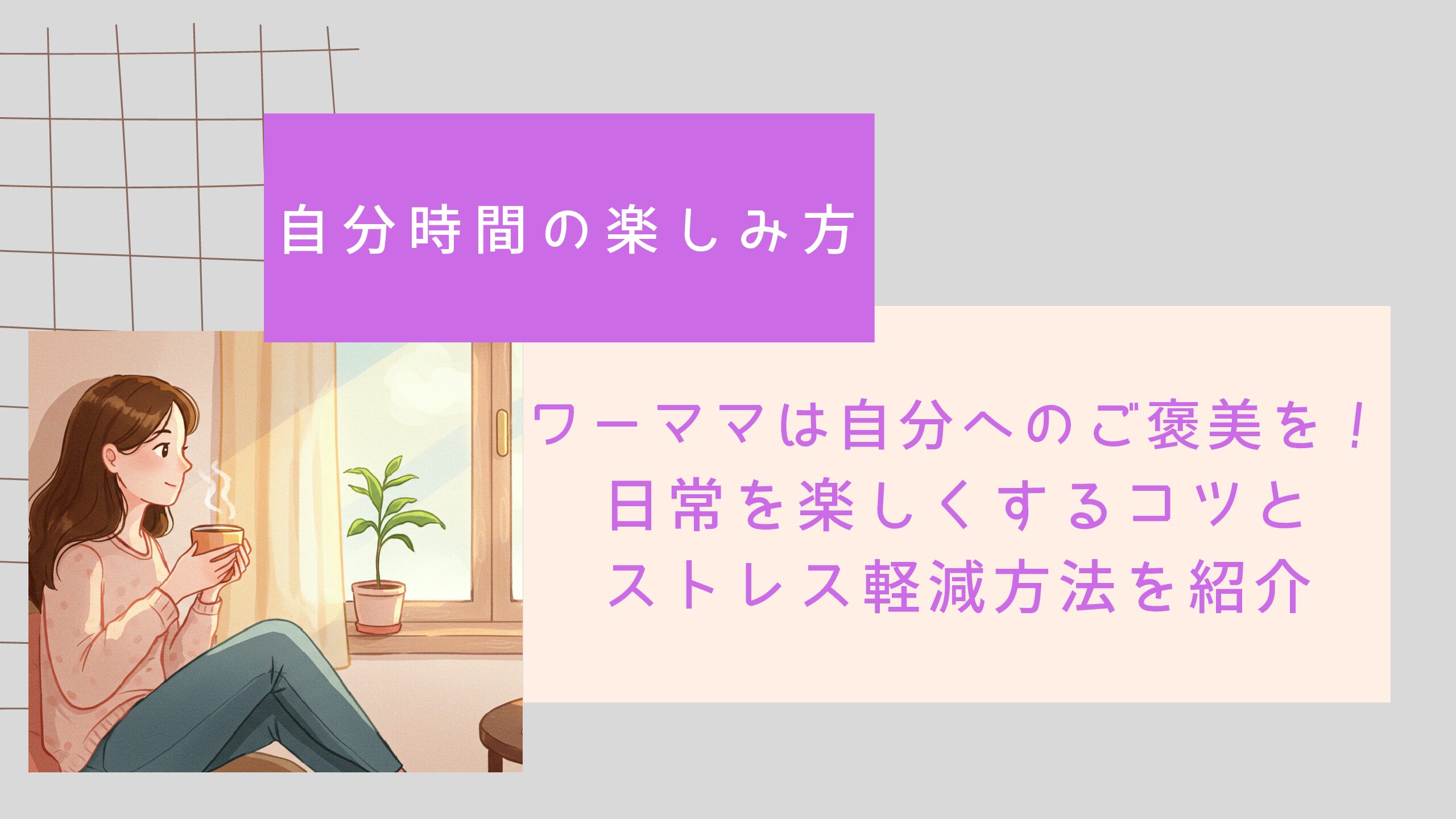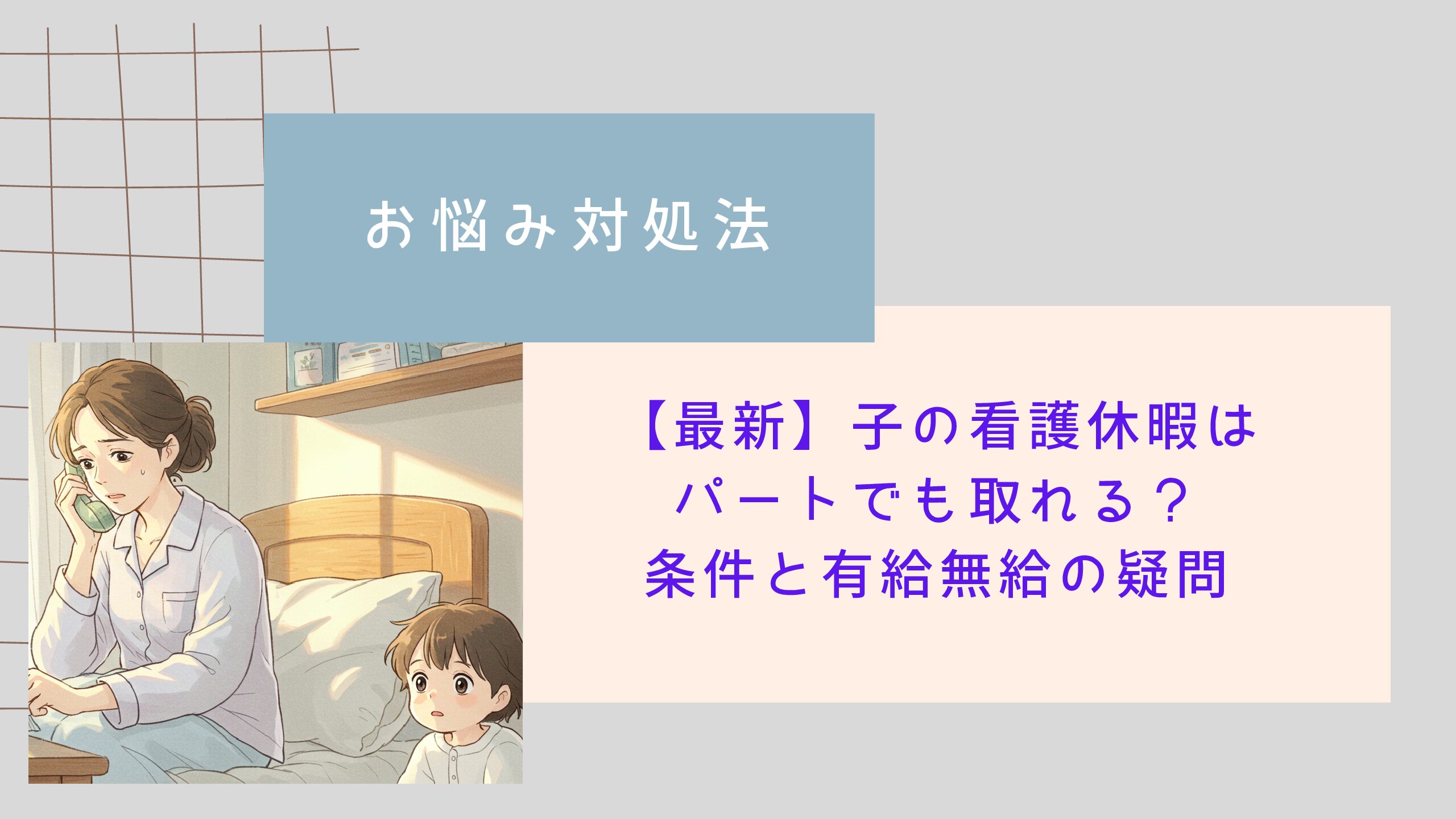ワンオペの日、こどもをお風呂に入れるのがしんどい、、と感じて検索してくださった方へ。
赤ちゃんとのバスタイムは楽しい時間のはずなのに、ひとりで全てをこなすとなると本当に大変ですよね。
そこでこの記事では、事前の準備から具体的な手順、命の危険を守るための注意点などを解説しています。
また「赤ちゃんがお風呂でギャン泣きするのはなぜ?」「ママがお風呂に入ると泣く理由は?」といった疑問への回答や、お風呂を嫌がるこどもを入れるコツなどにもふれています。
さらに「お風呂の待たせ方」「自分自信のお風呂の入り方」「2人育児、3人育児の場合はどうするか」「入れるのは何歳くらいで楽になるのか」「ゲットするべき便利グッズの紹介」など幅広くご紹介しています。
ワンオペでお風呂を少しでも気楽にする具体策をできるだけ盛り込みましたので、是非参考にしてください。
記事のポイント
ワンオペ お風呂 しんどい状況を乗り切るコツ
お風呂に入れるのは何時頃がよいかを考える

赤ちゃんをお風呂に入れる最適な時間帯は、家庭の生活リズムや授乳間隔に大きく左右されます。
一般的に、体温が自然に上昇しやすい18〜20時のあいだに入浴することで、体温が徐々に下がるタイミングで眠気を誘発し、就寝リズムを整えやすくなります。
ただし、月齢によっても理想的な時間帯は異なります。
生後3か月未満の新生児期は授乳間隔が短く、授乳後30分ほどの落ち着いたタイミングを選ぶのが安全です。
生後半年を過ぎると生活リズムが安定してくるため、家族の夕食前後など、一定のパターンを固定すると親子ともにストレスが減ります。
また、夜遅すぎる時間帯の入浴は避けることが望ましいとされています。
入浴による体温上昇が睡眠導入を妨げたり、皮膚乾燥を悪化させるおそれがあるためです。
乳幼児の肌は角質層が薄く乾燥や温度変化に敏感なため、お湯の温度は38〜39℃前後、
入浴時間は5〜10分程度が目安です。(出典:厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド」)
準備から手順、注意点を解説してスムーズに

ワンオペでお風呂に入れる際に最も重要なのは「段取りの一貫性」です。入浴前の準備を徹底しておくことで、事故防止と時短が両立します。
まず、浴室・脱衣所の温度を25〜28℃程度に保ち、赤ちゃんが寒さを感じない環境を整えます。
特に冬場はヒーターを事前に稼働させ、室内の温度差を最小限にすることが大切です。
次に、タオル・ベビーソープ・着替え・保湿剤などの必要物を、片手で取れる位置にまとめておきましょう。
手順としては、以下のようなイメージです
- 脱衣所で衣服を脱がせ、体温を確認する
- お湯の温度を38〜39℃で設定する
- 頭から順にやさしく洗い、すすぎ残しを防ぐ
- 上がったらすぐにタオルで包み、保湿剤でケアする
また、赤ちゃんの首がすわる前後では、抱き方を変える必要があります。首がすわっていない時期は、頭を支えるように「C字抱き」を意識し、首を固定しながら洗います。
首がすわった後は、バスチェアやバスサポートを活用して、親が両手を自由に使えるようにすると安全性が高まります。
赤ちゃんがお風呂でギャン泣きするのはなぜか理解する

赤ちゃんが入浴時にギャン泣きするのは、単なる「気分」ではなく、環境刺激と生理的反応の複合要因によるものです。
まず第一に、お風呂は赤ちゃんにとって五感刺激の多い環境です。
水音、温度変化、照明、湿度、親の動きなど、すべてが一度に変化するため、不安や恐怖を感じやすくなります。また、入浴直前の空腹や眠気が泣きの引き金になることもあります。
対策としては、入浴のタイミングを空腹時・眠気のピーク時に避け、泣いた際には「無理に進めず一度中断する」柔軟さが大切です。
また、赤ちゃんの視覚と聴覚に安心を与えるために、入浴中にやさしく声をかけ続けたり、短い歌を歌うのも効果的です。
これは「情動調整(emotional regulation)」という心理的概念に基づき、親の声や表情が赤ちゃんの自律神経を安定させる働きを持つことが知られています
ママがお風呂に入ると泣くときの対処法

赤ちゃんが「ママが浴室に入る=自分から離れる」と認識して泣くのは、分離不安(separation anxiety)によるものです。
生後6〜8か月以降に顕著に見られ、これは発達の正常な段階です。
この時期の赤ちゃんは、ママの存在を「視覚的・聴覚的手がかり」で安心する傾向が強いため、完全に離れず、少しでも気配を感じられる工夫が有効です。
具体的には、以下のような工夫をしてみるのはいかがでしょうか。
- 浴室のドアを数センチ開けて声を聞かせる
- 「これからママお風呂ね」と声かけしてから入る
- 脱衣所でお気に入りのぬいぐるみを持たせる
- ベビーモニターを活用して泣き声を即確認する
また、短時間で済ませるために、**時短入浴(3〜5分以内のシャワー中心)**を導入してみるのもおすすめです。
育児ストレスが蓄積している場合、ママ自身の休息を後回しにせず、夜間や休日にパートナーと交代する「お風呂当番制度」を作るのも有効です。
嫌がるこどもを入れるコツを身につけよう

1歳以降の子どもは、自我が芽生え始め、「お風呂イヤ!」と強く拒否する時期が訪れます。
この行動は発達の一環ですが、毎晩の入浴を巡って親子のストレス源になることも少なくありません。
拒否反応の背景には、「寒い」「怖い」「面倒」などの感覚的・心理的理由があります。
そのため、説得ではなく環境と導線を工夫するアプローチが効果的です。
具体的には、
- お風呂用おもちゃ(泡遊び、水鉄砲など)で楽しさを演出する
- ステップ入浴法:湯船の外で足だけ→腰まで→全身と徐々に慣らす
- お風呂前の約束タイム:「お風呂のあとはジュース」など小さなご褒美を設定
- 入浴後のルーティン(保湿→パジャマ→絵本)を固定して見通しを与える
「嫌がる=わがまま」ではなく、未知の環境に対する自然な防衛反応と捉えることで、親側のストレスも軽減できます。
特にイヤイヤ期の対応では、「強制よりも一緒に楽しむ姿勢」が、長期的には入浴習慣の定着につながります。
お風呂の待たせ方で安全と安心を確保する

ワンオペ育児における最大の課題は「目を離す時間をいかに安全に確保するか」です。
お風呂の待たせ方には、年齢・環境に応じた工夫が求められます。
生後3か月までは、バスルームの外にハイローチェアやベビーバスケットを設置し、赤ちゃんを目の届く位置で待機させましょう。
浴室と脱衣所をつなぐドアを少し開けておき、声が届く距離を保つのがポイントです。
動きが活発になる6か月以降は、転倒防止策が必須になります。滑り止めマットを敷き、周囲に落下しやすい物を置かないよう整理しておきましょう。また、待機中の冷え対策として、乾いたタオルで包み、室温を一定に保つことが重要です。
赤ちゃんが泣いた際には、焦らず一度浴室から出て様子を見ましょう。
短時間の入浴でも安全第一を優先することが、長期的な育児ストレス軽減につながります。
消費者庁の「家庭内事故データ」(2023年度)によると、乳幼児の入浴中事故の約6割が「一瞬の目離し」によって発生しています。
短時間であっても、完全に視界から外さない工夫を取り入れることが最も効果的な予防策です。(出典:こども家庭庁「子どもの事故防止ハンドブック」)
ワンオペ お風呂 しんどいを軽くする実践アイデア
自分のお風呂の入り方を工夫してリフレッシュ

育児中は、自分の入浴時間を確保すること自体が大きな挑戦になります。
特にワンオペの日は、赤ちゃんを寝かしつけてからの数十分が唯一のリフレッシュタイムという方も多いでしょう。
そんな状況でも、疲れをため込まないためには「限られた時間で心身を温め、気分を切り替える工夫」が重要です。
たとえば、シャワーで全身をしっかり温めたあとに足湯や半身浴を取り入れることで、血行促進や冷えの改善が期待できます。
入浴による深部体温の上昇は睡眠の質にも直結しており、寝る約90分前に入浴を終えると、自然な体温低下によって眠りに入りやすくなると報告されています(出典:厚生労働省 e-ヘルスネット「快眠と生活習慣」)。
また、浴室をあらかじめ温めておくことで、短時間でも体温が保たれやすくなり、ヒートショックの予防にもつながります。
もし湯船に入る余裕がない日は、「全身をシャワーで温めてから、首筋や足元を中心に温かいお湯をかける」だけでも血流改善に効果的です。
さらに、赤ちゃんの寝かしつけ後や、パートナーの在宅時間に合わせて入浴時間を調整することで、心の余裕も生まれます。
自分の健康とリラックスを軽視せず、「短時間でも癒される工夫」を持つことが、育児を長く続けるうえで大切なセルフケアになります。
2人育児、3人育児の場合は段取りがカギ

子どもが2人以上いる家庭では、お風呂の段取りが格段に複雑になります。1人ずつ洗う場合は待機時間が長くなり、同時に入ると安全性の確保が課題になります。
そのため「順序」「動線」「安全対策」の3つを意識した段取りが欠かせません。
多くの家庭では「上の子 → 大人 → 下の子」という流れで入浴を進めるのが効率的です。
上の子を先に洗い、湯船で待たせている間に自分の体を洗い、最後に下の子を迎える形です。
湯温は38〜39℃と低めに設定し、水位は胸より下に抑えることで、のぼせや転倒事故のリスクを軽減できます。
また、下の子の待機場所を事前に確保しておくことも重要です。
脱衣所にバウンサーやハイローチェアを設置し、視界の中で安全に待たせられるようにします。
兄弟の年齢差が大きい場合は、上の子に「洗面器でお湯をかけてあげる」などの簡単なお手伝いをお願いすると、協力意識を育むきっかけにもなります。
一方で、2人・3人育児では親の体力的な負担も大きくなりがちです。
お風呂を入れる時間帯を固定する、もしくは週に数回だけパートナーが対応する日を設けるなど、「継続可能なルール作り」を意識することで、無理なく続けられるお風呂習慣が定着します。
何歳くらいで楽になるか目安を知っておこう

お風呂のワンオペが「少し楽になる」と感じられる時期は、子どもの成長とともに訪れます。
一般的な目安としては、生後6か月頃からお座りが安定し、9か月前後でつかまり立ちを始めることで、親の支えが減り始めます。
1歳半を過ぎると、短時間の待機が可能になり、2歳頃には「体を洗う」「湯船に入る」といった入浴行動の意味を理解できるようになります。
3歳を超えると自分で体を洗う練習を始めたり、シャワーを持つなど簡単な動作を手伝えるようになり、ワンオペの負担は大幅に軽減されます。
ただし、成長のスピードや性格には個人差があり、「できる・できない」を年齢で判断することは避けましょう。
むしろ重要なのは、「その子のペースに合わせて段階的に任せる」ことです。
たとえば、最初はお湯を手ですくって体にかけるだけでも十分なステップアップです。
焦らず、安全第一で少しずつ自立を促していくことが、親子双方のストレスを減らす近道です。
便利グッズの紹介で負担を減らす

ワンオペ育児におけるお風呂時間を支えるのが、実用性に優れた便利グッズです。
その中でも特に人気が高いのが、赤ちゃんを安定した姿勢で支えられる「ラッコハグ」シリーズです。
| ピープルHugシリーズラッコハグ+(LaccoHug+)color:ソフトアプリコットPI-036 価格:9,030円(税込、送料別) (2025/10/25時点) 楽天で購入 |
背もたれ構造によって抱っこの姿勢をサポートし、洗髪中でも赤ちゃんを安全に待たせることができます。
また、「ラッコハグプラス」には底水栓が搭載されており、排水がスムーズに行えるため、後片付けの手間が大幅に減ります(出典:ピープル株式会社 公式サイト)。
その他にも、転倒防止の「滑り止めバスマット」、赤ちゃんを安定して支える「バスチェア」や「バウンサー」、湯冷めを防ぐ「バスローブ」なども効果的です。
| \10/25迄最大15%OFFクーポン!楽天1位・秋用/バスローブ ガウン マイクロファイバー ルームウェア 高級 膝丈 ひざ丈 時短 速乾 保温 bathrobe ふわふわ 通気 薄手 マタニティ 子育て レディース メンズ 女性 部屋着 速乾 フィットユース 結婚出産祝い 蛍光染料不使用 価格:2,880円~(税込、送料無料) (2025/10/25時点) 楽天で購入 |
特に「泡で出るタイプのベビーソープ」は、片手でも使えるため、赤ちゃんを支えながらでも洗いやすく、多くの家庭で重宝されています。
| 【P10倍★10/27 9:59まで】【公式】 セタフィル ベビー ウォッシュ&シャンプー 400ml 赤ちゃん 新生児 0歳 子供 子ども キッズ ヘアシャンプー 低刺激 敏感肌 乾燥肌 ベビーシャンプー シャンプー 沐浴 1歳 2歳 3歳 ボディソープ 弱酸性 頭 価格:1,990円(税込、送料無料) (2025/10/25時点) 楽天で購入 |
これらの便利グッズを上手に取り入れることで、入浴中の安全性が高まり、ママの体力的・精神的負担も軽減されます。無理をせず「道具の力を借りる」という発想を持つことが、ワンオペ育児を乗り越えるための賢い選択です。
まとめ:ワンオペ お風呂 しんどいを少しでも楽にするために

今回の記事のポイントを以下にまとめました。以上を意識しながら、無理のない範囲で工夫を取り入れていけば、ワンオペお風呂のしんどさを少しずつ軽くできはずです。気負いせずやっていきましょう。